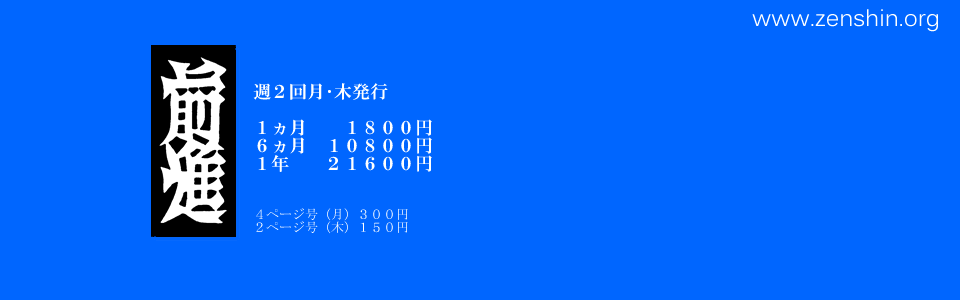繰り返すな戦争-天皇制と戦争- 第2回 戦争責任は昭和天皇にある 最高指揮権を握り軍隊に命令
週刊『前進』02頁(3025号02面03)(2019/04/04)
繰り返すな戦争
-天皇制と戦争- 第2回
戦争責任は昭和天皇にある
最高指揮権を握り軍隊に命令

(写真 1937年12月の南京大虐殺直後、白馬にまたがって閲兵し兵士を鼓舞する昭和天皇【1938年1月8日】)
去る2月7日、韓国の国会議長が、日本軍軍隊慰安婦とされた女性たちへの日本の天皇による直接謝罪を提言した。安倍政権は血相を変えてこれに猛反発し、韓国政府に対して発言の撤回と謝罪を居丈高に要求している。だが本シリーズの第1回(3021号掲載)で明らかにしたように、かつての戦争がすべて、天皇が最高責任者であった「天皇の軍隊」によって行われたことはまぎれもない事実だ。現在の象徴天皇制は天皇の戦争責任を免罪し、逆に天皇の名のもとに行われた極悪の戦争犯罪を隠蔽(いんぺい)した上に成り立っている。このことを直視することは、日本の労働者民衆にとって絶対にあいまいにできない課題である。
代替わりの過程で大弾圧
1901年生まれのヒロヒトは、病弱な大正天皇の代理として21年から摂政を務め、26年12月に昭和天皇となった。この大正から昭和への天皇代替わりの過程は、日本とアジアの人民を血みどろの戦争と暗黒の時代に引きずり込む歴史的転換期となった。17年ロシア革命と18年ドイツ革命は、ヨーロッパに暗い影を落としてきた2大君主制を崩壊させ、世界中の労働者や抑圧された民族を奮い立たせた。日本では労働運動が一大高揚期を迎え、20年には初のメーデーが開催された。横暴な軍部への怒りや普通選挙権要求の声も高まり、天皇・皇室を批判する「不敬事件」も多発した。19年、朝鮮では3・1独立運動、中国では5・4抗日闘争が日本の侵略の前に立ちはだかった。
こうした状況への危機感を、ヒロヒトは21年8月の日記に「世界の思想界は大に乱れ、過激思想は世界に広まらんとし、労働問題はやかましくなりたり」と記している。軍部や財閥を中心とした日本の支配層は、天皇代替わりを機に国内階級闘争を鎮圧し、ぐらついた天皇・皇室の権威を立て直そうとした。特に深刻化していた軍隊の士気低下に対し、天皇への絶対服従の軍紀を再確立することが急務だった。ヒロヒトもまた摂政就任直後から軍隊の掌握に務めた。
26年12月に大正天皇が死ぬと、早くも27年5月には新天皇ヒロヒトの命令で中国・山東省への侵略出兵を開始。28年には本格的に代替わりの儀式が始まるが、「儀礼と宣伝を通じた新天皇の創出過程は、思想統制装置の顕著な増強・拡張と手を携えていた」(ハーバート・ビックス著『昭和天皇』)。この年、全国で労働者・学生1600人が一斉逮捕された3・15弾圧に続き、治安維持法の改悪と全国への特高警察(思想警察)の設置が、いずれも緊急勅令(天皇の命令)で行われた。
そして12月には過去最大規模の大礼特別観兵式・観艦式が行われ、陸海軍を閲兵するヒロヒトの様子が新聞やラジオで大々的に報道された。「大正天皇の弱さが大正デモクラシーの台頭を促したのに対して、昭和天皇の即位はその終焉(しゅうえん)をもたらし……君臨し、かつ統治する天皇の神格化の完成を宣言した」(同)。こうして日本は破滅的な15年戦争へと突き進むのである。
戦後の日本では、「もともと昭和天皇は平和主義者だったが、当時は天皇ですら軍部の暴走を止められなかったのだ」というつくり話が流布されてきた。だがこれは歴史の事実に反する大うそだ。ヒロヒトは名実ともに戦争の最高指導者であり、意識的な戦争放火者だった。
侵略の拡大は天皇の意志
戦前の帝国憲法では、天皇は国家の唯一最高の統治者、陸海軍の最高指揮者とされ、天皇直属の軍令機関(大本営、陸軍参謀本部、海軍軍令部)を除き、軍令事項には政府も議会も一切関与できなかった。たとえ軍部が先走っても、天皇の裁可なくして戦争継続は不可能だった。31年9月、陸軍の出先機関である関東軍が中国東北部への侵略戦争(満州事変)を起こした際、天皇は自分の命令なく軍を動かした現地の司令官らを一切とがめなかった。さらに天皇は32年1月8日の「勅語」で、関東軍の行動を「自衛の必要上」によるものと断定し、「皇軍の威武を中外に宣揚せり」と絶賛した。天皇が公式に「皇軍」という言葉を使ったのはこれが初となる。こうして中国侵略戦争は天皇の名で「自衛」という大義名分を与えられ、疑問や批判は一切許されなくなった。
中国全土に侵略を拡大する契機となった37年7月7日の盧溝橋事件では、現地の日本軍は戦闘拡大を避けてすぐに中国軍と停戦協定を結んだ。参謀本部でもソ連の介入を恐れ不拡大を主張する声が上がった。だが天皇は拡大論を支持し増援部隊の派遣を決定、泥沼の戦争へと軍を進めた。
同年11月には宮中に軍の最高司令部である大本営が設置され、以後「大本営政府連絡会議」と称する会議体が内閣以上の権限をもって重要国策を決定することになった。ここに天皇自身が参加する場合を「御前会議」と呼んだ。米英を相手とするアジア太平洋戦争開戦は、41年11月5日の御前会議で決定された。天皇はこれに先立ち開戦派の東条英機を首相に任命し、軍部には前もって戦争準備を命じていた。
延命のため人民を犠牲に
天皇は対米英開戦の「詔書」で、全国民に対して一人の例外もなくそれぞれの持ち場で全力を尽くし戦争を完遂せよと命令した。開戦当初、天皇は緒戦の勝利に「余り早く戦果が挙がりすぎるよ」と有頂天になり、連合国との早期講和をも考えた。だが米英は日本と妥協する気など毛頭なく、42年5〜6月から反転攻勢を開始した。
戦況が悪化すると、天皇は日に日に焦りを募らせ、大本営会議に出て活発に発言するようになった。「どこかで米軍をたたきつけることはできぬか」「なぜ攻勢に出ないのか」と参謀総長らに繰り返し問い、しきりに「決戦」を叫んで戦局を打開する決定的な一撃を要求した。この決戦主義に引きずられ、日本軍はますます無謀な作戦に傾斜していった。こうした天皇の具体的な戦争指導については、井上清著『天皇の戦争責任』や、最近の研究では山田朗著『昭和天皇の戦争』などに詳しい。
敗戦が不可避となっても天皇は降伏を引き延ばし、自らの延命のためだけに多くの人々を死に追いやった。45年2月には元首相・近衛文麿が天皇への上奏文で「敗戦はもはや必至」と述べ、「国体護持」すなわち天皇・皇室の維持のためには今すぐ連合国に降伏するのが得策だと提言した。ところが天皇は、「(国体護持のためには)もう一度戦果を挙げてからでないとなかなか話は難しい」とこれを却下し、さらに半年も戦争を継続した。この天皇の悪あがきのために沖縄は「捨て石」にされ、日本中が空襲で焼け野原にされ、膨大な数の兵士や一般市民が命を落とし、ついには広島・長崎への原爆投下にまで至ったのである。
45年8月15日の終戦は、決して「国民を救うための聖断」などではなく、連合国に天皇制存続を認めさせることと引き換えの取引に他ならなかった。
終戦後、天皇は自らが命令した沖縄戦について「まったくばかばかしい戦闘であった」(『昭和天皇独白録』)と吐き捨てた。こんな人物が、なぜ何の責任も問われず、何の裁きも受けずに延命できたのか。
次回はそれを明らかにするために、戦後憲法の成立過程と「象徴天皇制」の本質を見ていきたい。