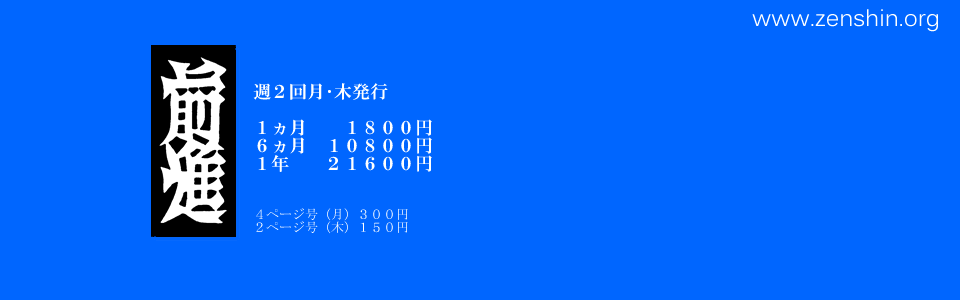第14期党学校で
週刊『前進』06頁(2632号06面02)(2014/05/19)
第14期党学校で
労働者階級を主体にして執筆された「50年史」 前田文武
今期の党学校は、これから勝負に打って出るために『50年史』の刊行と一体的に党史総括をするものとしてかちとられました。とりわけ私にとっては、60年・70年安保はもちろん、対カクマル戦もまったく経験していない年代であり、党に結集してからも日が浅いので、革共同の歴史と闘いを総括し学ぶことは大変有意義なものであったと思います。革共同の歴史と闘いは、多くの同志によるまさに格闘につぐ格闘によって積み上げられてきたものであることをはっきり感じました。もちろん私は、革共同の主張・闘いに強く共感を覚え、展望を感じたからこそ結集したわけですが、多くの同志たちが現実と理論の両面に真っ向から立ち向かい、人生をかけて闘ってきたからこそ、そのような獲得力をもっているのだと思います。
何より、労働者階級の階級としての闘い、そして階級の先頭に立つ党としての闘いという位置づけをつねに忘れないことが、私としては大切な点だと思います。「誰が、いつ何を思いついたか」とか「いつの誰と誰の会談で決まった」というように個人を主体にするのではなく、あくまで労働者階級を主体にして、階級がどのように時代に立ち向かってきたのかという視点で書かれたのが革共同の『50年史』であり、革共同の思想を体現していると思います。
このような革共同の思想と闘いをしっかりと自分のものにして、革命に向かって闘っていきたいという決意を新たにしました。
職場を丸ごと団結させるのが労働組合だ 高村宏信
党学校には、3期連続参加しました。『共産党宣言』には、「これまでのあらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史」とあるが、階級闘争の歴史の中で、奴隷や農民が反乱した時代には、奴隷や農民が国家権力を奪取し、新たな社会を建設するための歴史的条件はまだ成熟していなかった。それは資本主義社会の到来と資本主義社会の墓掘り人であるプロレタリア(労働者)の登場を待つしかなかった、とある。
今そういう時代に生きているのだ、とあらためて実感! そして共産主義について、「遠い未来の理想社会」ではなく、労働者階級がブルジョア国家権力を打倒して全権力を握るならば、すぐにでも着手できる、というフレーズも実感できるようになった。
一番強烈に感じたことは、「労働組合=基礎的団結形態」が、職場の全労働者を「丸ごとひとつにする」ことのできる団結形態だということ。
資本のあらゆる分断支配を打ち破って「階級として一つ」になったとき、労働者は真に階級として自己を形成する。労働組合が資本との非和解の対峙・対決を通して職場生産点に労働者の階級的団結をつくりだすことこそが、資本によって組織された労働組合を新社会建設のための全労働者の主体的・積極的・意識的な共同体的労働組合へと転化していく。新自由主義と大恐慌の中で、こういう闘いを進めていかなくてはならない、またこれしかないということを確認することができました。
日共・カクマルとの党派闘争の意義を確認した 福原 豊
われわれはスターリニストと決別し、トロツキー教条主義と分裂し、カクマルをたたき出して新しい革命党をつくり出した。日共とカクマルと対決しぬくことは、マルクス主義の党の歴史的復権にとって決定的な意味をもってきた。「現代革命への挑戦」とは、この対決の決着ということでもある。カクマルの襲撃、それに対する二重対峙・対カクマル戦、さらには3・14復讐戦争は、いま振り返っても激しく巨大なものがあった。反革命に対する労働者階級と党の必死の反撃であった。
そのことは、その後の国鉄分割・民営化攻撃の現実と重ね合わせるとはっきりする。「自殺者200人」は単に新自由主義の激しさだけではなく、カクマルを抜きには考えられない。また社民やスタのあり方をあらためて問う問題でもある。カクマルの襲撃とそれへの内戦的反撃、国鉄分割・民営化に抗しえなかったすべての勢力は、新自由主義攻撃を見据えることができないでいる。
「現代革命への挑戦」に対抗して昨年2回の「50周年政治集会」を開催したカクマルは、「対中核派戦争」も「動労カクマル」も総括できず、「反ファシズム」論で小ブル的な自己総括をした。
最末期帝国主義の絶望的延命形態である新自由主義の反マルクス主義、反労働組合的団結。これは新自由主義の弱点でもある。この弱点とは、階級闘争的に言えば、カクマルを始め体制内左翼との党派闘争の決定的な意義を確認するものだ。