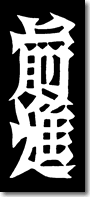第2次再審勝利へ 三多摩「救う会」の決意 加納敏弘
第2次再審勝利へ
三多摩「救う会」の決意
労働者階級は必ず決起すると確信
革命の力で星野同志を奪還できる
三多摩・星野文昭さんを救う会 加納敏弘
昨年11月27日、星野文昭同志と再審弁護団は、27点もの新証拠を添えて第2次再審請求書を東京高裁に提出した。
今回の新証拠で「きつね色の服を着た」人物が存在したこと(しかも2人も!)、それが星野同志とは別人だったことが明らかになった。「『きつね色』というのはKrの見間違い。声や後ろ姿で星野が犯人であることは確実」という最高裁の主張はこれで崩される。
階級的共同性を
とりわけ素晴らしいのは、星野さん自身の「陳述書」だ。
「人は、本来一人では生きていけず、自分だけよければいいという利己的な存在ではなく、誰もが人間らしく生きられることによって心から満たされる存在であり、それを実現する力を持つ存在である。その人間的共同性、力が世の中を誰もが人間らしく生きられる世の中に変えていくし、同時に私の無実には無罪を、釈放をの訴えが人々の心に届き広がり、それを実現していくことができると確信している」
ここにあるのは、自らの闘いの勝利性と、労働者階級は階級的共同性を取り戻し必ず決起するという確信だ。国家権力に一筆書いてなんとか出してもらおうという意識は微塵(みじん)もない。
昨年の星野全国総会で私たちは、塩川一派とそれに追随する人びとの掲げる仮釈放路線を完膚無きまでに批判し、決別した。彼らに共通していたのは「労働者は革命になんか絶対に決起しない」という階級不信だった。
彼らからは、沖縄が「復帰」後38年たった現在も基地地獄に置かれている現実、本土に職を求めてやってきた沖縄の青年労働者が真っ先に「派遣切り」にあって、職場からも住む家からもたたき出されている現実に対する怒りがまったく感じられなかった。沖縄の青年労働者のなかに「星野」を持ち込もうとか、青年労働者の怒りの決起と結びついて星野同志を奪い返そうとかいう気概はまったくなかった。
あらためて、1971年11・14渋谷暴動闘争とは何だったのかということだ。それは、「本土復帰」という沖縄人民の「願い」に応えるかのようなポーズをとって、その実、沖縄を永久に基地地獄にし、侵略戦争の拠点にする「沖縄返還協定」批准に反対する実力闘争だった。本土と沖縄の分断支配をのりこえて、数千人の青年労働者と学生が「すべてをかけて」決起した。当時の佐藤政権は、公安条例を盾に一切の集会・デモを禁止し、国会では強行採決を行った。
労働者との団結
だから、革共同と本土の青年労働者・学生は「退路を断って」決起することで、11・10ゼネストをやり抜いた沖縄の労働者人民と団結する道をとったのだ。国家権力は、ここに「革命のヒドラ」を見た。だから無実を承知で星野同志を「犯人」にデッチあげ、35年も投獄しているのだ。
今、沖縄は「革命の火薬庫」の導火線に火がつき、まさに爆発寸前だ。鳩山民主党・連合政権は、選挙公約で普天間基地の「国外・県外移設」を言いながら、結局「キャンプ・シュワブ」を決定しようとしている。沖縄人民をあくまで見殺しにするということだ。
沖縄の「人士」たちの多くは、労働者階級の力に依拠することができず、民主党政権の旗振り役を任ずるに至った。その化けの皮がはがれた今、沖縄の労働者階級の歴史的決起が絶対に始まる。なぜなら「基地と労働者」「戦争と労働者」は絶対に相いれないからだ。
かつて「革命でしか星野は奪還できない」ともいわれ、それはややもすれば「星野奪還」を「彼岸化」する論理だった。しかしいまや「革命の力で、労働者階級の力で星野を奪還できる」と言い切ることができる。労働者の中に星野闘争を広めよう。