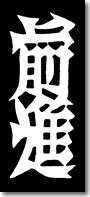映評 マイケル・ムーア監督「キャピタリズム」
映評 マイケル・ムーア監督 「キャピタリズム」
本気で資本主義を断罪
労働者に反乱のメッセージ
圧倒的自信と確信をもって薦めたい映画だ。マイケル・ムーア監督は真剣だ。そしてアメリカの普通の労働者の意識、感覚とぴったり波長が合っている。なによりも本気で怒っていることがビンビン伝わってくる。彼は本気で資本主義を断罪している。ブルジョアどもを縛り首にしたいと心から願っている。ストレートに労働者に反乱を呼びかけている。若い人が見れば「アメリカってこんなに労働者的な国なの?」と言うだろう。
マイケル・ムーアは今回初めて日本に来たそうだ。「これは日本の問題でもあるから」と言っている。日本の興行主は、この映画の毒がどの程度か測りかねている。なんとか薄めて、人畜無害のウォール街のドタバタ劇であるかのように打ち出したいわけだ。マイケル・ムーアの方は、とにかく映画館に観客を引き込めばおれの勝ちなんだから、どうにでも利用してくれという腹だ。
日本語タイトルは『キャピタリズム—マネーは踊る』というが、原題を直訳すると「資本主義—ある愛の物語」だ。この方がずっとすごみがある。鳩山の「友愛思想」(そしてそれを美化するさまざまの連中)などとはスケールも深みも違う。マイケル・ムーアは資本主義の〈お金に対する倒錯した愛>を皮肉っているのだと朝日新聞に書いてあったけど、ちょっと違うだろう。
「愛の物語」というのは、要するに革命のことだ。映画は、昨年秋、オバマ大統領の誕生とウォール街の崩壊が同時発生した情勢そのもの(09年年頭ころまで)を映像化している。ついにアメリカの労働者は立ち上がり始めたが、始まったこの革命の物語をトコトン最後まで生きぬき、やりきる力が労働者階級にはあるのか、絶対にあると言いたい、というのが労働者階級の子マイケル・ムーアの心のメッセージだ。
オバマはルーズベルトを引き継いで労働者のために登場したかのように装った。だからこそ地すべり的に勝利した。マイケル・ムーア自身そうなって欲しいと願っていたから、そのように描いた(30年代アメリカ階級闘争の歴史的総括は大事だ)。しかし、たちまち幻想ははげ落ちた。ムーアは、オバマがアフガニスタンへの3万人増派決定の演説(日本時間12月2日午前)をした直後、オバマを弾劾するメッセージを発している。これはアメリカで大きく取り上げられている。
ムーアはこの映画で、キリストを埋葬して労働者自身が立ち上がらなければと執拗(しつよう)に訴えている。キリストとはオバマでもあるし、実はムーア自身でもあるのだ。
08年に闘われたシカゴ(オバマの地元)のリパブリック・ウィンドウズの工場占拠の現場が生き生きと描かれている。
最後に流れるラップ調(?)のインターナショナルが実にいい。ここだけは、日本語字幕の翻訳者の努力を多としたい。終わって、拍手しようと周りを見ると館内がシーンとしていた。若い人たちもそれなりにいるのだが、ただ黙って座っている。あまりにストレートな扇動にとまどっているのだ。しかしこの突き刺さった困惑は何かの始まりになりえる。(N)